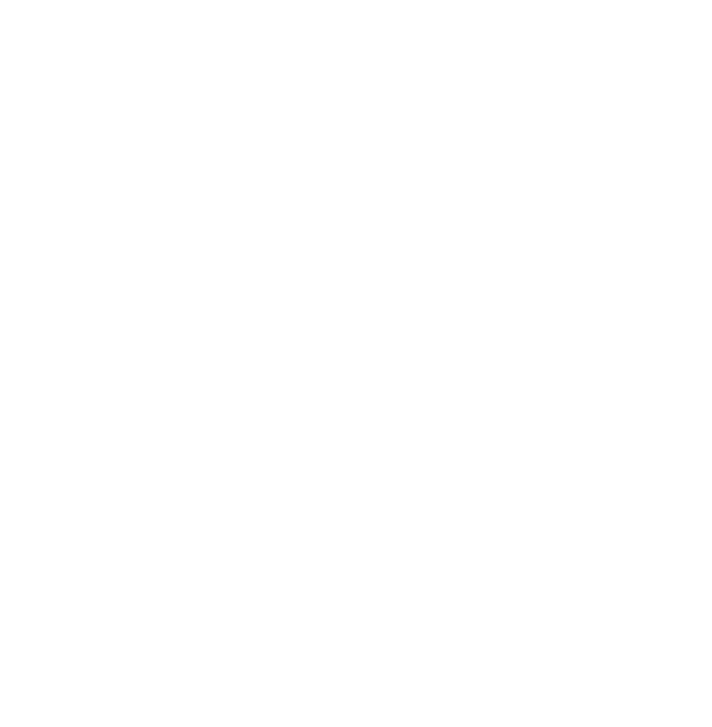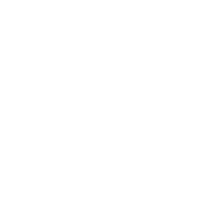『親子で学ぶ はじめての将棋教室』 レポート
10月25日、日本将棋連盟つくば支部のご協力のもと、「親子で学ぶ はじめての将棋教室」を開催しました。
今回はその様子をお届けします。
▮将棋クイズからスタート
「将棋って難しそう」「ちょっと堅いイメージがある」──そう感じている方も多いのではないでしょうか。
そんな空気を一瞬で和ませてくださったのが、講師の日本将棋連盟つくば支部・仁衡さん。
明るい声で「まずは将棋クイズからいきましょう!」と会場に呼びかけると、
「将棋はどこの国の発祥でしょう?」など、思わず“へぇ!”と声が出るような質問が続き、会場が笑顔に包まれました。

▮駒の動かし方を学ぼう
将棋の基本は、駒の動かし方を覚えること。
仁衡さんが用意してくださったリーフレットを参考に、親子でひとつずつ確認していきます。
「飛車がパワーアップすると“竜”になるんだよ」と説明があると、
「ドラゴン?!」と目を輝かせる子どもたち。
そんなやりとりに会場は終始なごやかで、自然と笑い声が広がっていました。

▮実戦の前に大切なこと
将棋には、“自ら負けを認める”という独特の文化があります。
最後まであきらめない気持ちも大切ですが、現実を受け入れ、潔く次につなげる姿勢は、まさに忍耐力と判断力を養う学びそのもの。
また、使った駒や盤を丁寧に片づけることも教えのひとつです。
“道具を大切に扱う”という心が、将棋の精神にも通じているのだと感じました。

▮いざ、対局!
振り駒で先手を決め、いよいよ実戦スタート。
大人も子どもも同じ盤上で真剣勝負です。
「お父さんに勝てた!」と嬉しそうな声をあげるお子さんの姿もあり、
勝ち負け以上に、親子で向き合う時間の尊さを感じるひとときとなりました。

▮少しだけ裏話
実は今回の将棋教室の企画は、筆者自身の“将棋への想い”から始まりました。
羽生善治九段の99期達成のニュースをきっかけに興味を持ち、
父と毎朝一局指していた日々の中で「将棋って、素敵なコミュニケーションツールだな」と感じたことが原点です。
理性的に考える力、冷静な判断、そして相手を思いやる心。
子育ての中にもきっと活かせる要素がたくさんあります。
数年後、こうして「粋」でイベントとして実現できたことを心から嬉しく思います。
この体験をきっかけに、家庭で将棋が新たなコミュニケーションの架け橋になれば、
そして「プロを目指したい!」というお子さまが現れたなら──これほど嬉しいことはありません。
これからも、皆さまに楽しんでいただける体験をお届けしていきたいと思います。